

エスプレッシーヴォ[espressivo](伊)
2014年3月19日(水)
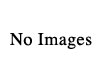
楽譜の中に[espressivo] エスプレッシーヴォと言う言葉がよくでてきますよね。この言葉は表情豊かにと訳されています。 語源はラテン語の[exprimere] ex「外に」、primere「押し出す」という二つの意…..
… ▶続きを読むフェイド・イン[fade in]
2014年3月19日(水)
フェイド・アウト[fade out]
2014年3月19日(水)
フィンガリング[fingering]
2014年3月19日(水)
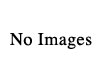
指使い、魔法使いでなくて、指の使い方のこと、人差し指、中指なんて言っていられないので 1、2、3、4と指に番号をつけて書いたり言ったりしますね。 何処で指をずらすか?ポジションを上げたり下げたりするか?どの弦で弾くか? …..
… ▶続きを読むフラジオレット[flageolet]
2014年3月19日(水)
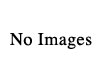
弦楽器で、弦のフレットの上を軽く押さえて、人工的に倍音を出す奏法。ハーモニックス。 マンドリンだと一番簡単なのは、開放弦で12フレットのところを軽く触れて弾くとオクターブ上の音が鳴りますね。7フレットだと5度上の音がなる…..
… ▶続きを読むゲネプロ[Generalprobe](独)
2014年3月19日(水)
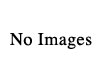
ゲネラルプローベの略なんだって、知ってましたか? オーケストラの総練習やオペラの舞台練習のこと。ヨーロッパでは一般に公開されます。日本でも 最近公開するのが多くなりましたね。最近はポピュラーの世界でもこの言葉を使うように…..
… ▶続きを読むフェルマータ[fermata](伊)
2014年3月19日(水)
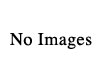
フェルマータについてですが、やたら伸ばせばいいというわけでもなく、リズム感を壊すということでもなく、 前にも書きましたが、流れを一時ストップすると言う意味です。 Fermataの語源はFermareです。 バスの停留所、…..
… ▶続きを読むグラーヴェ[grave](伊)
2014年3月19日(水)
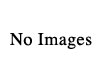
今日、ある楽曲の練習を生徒さんとしていて、 「Grave」 という表記が出てきました。 どうも、その演奏がグラーヴェに程遠いので「どういう意味か知ってる?」の質問に「ゆっくり・・・。」との答えが返ってきました。 「ゆっく…..
… ▶続きを読むグラツィオーソ[Grazioso](伊)
2014年3月19日(水)
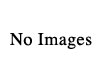
上品、優雅、愛らしい、繊細、しとやか グラツィオーソの語源は、ラテン語のグラーティアム grātiam です。 これはグラートゥス grātus 「好きな、好みに合う」「感謝」「喜び」「ありがたさ」「慈悲」「寛大さ」とい…..
… ▶続きを読む絶対音感[absolute hearing]
2014年3月19日(水)
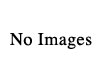
ある音の絶対音高を他の音と比べるので無く、直接「C」なら「C」と認識できる能力。 相対音感は、1つの音ではどの音かわからないけど、他の音と比較すれば識別できる。 絶対音感は「訓練によってできるようになる。」と思われている…..
… ▶続きを読むアゴーギク[Agogik](独)
2014年3月19日(水)
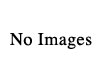
音楽学者リーマンによって定められた概念で、楽譜に指示されていない微妙なテンポの変化で 音楽をより生き生きとさせる手法、現象。いわゆる速度法。 パソコンで簡単な曲を演奏させてみるとはっきりわかるのですが、各音符を完全に同じ…..
… ▶続きを読むアナリーゼ[Analyse](独)
2014年3月19日(水)
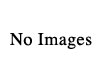
楽曲分析:音楽作品を、和音、形式、様式などの点から解析して、その構造を明らかにすること。 きちんと和音進行を研究したり、それぞれの変奏がテーマに対してどう言う割合で拡大・縮小されているか? とか 作曲家もびっくりするぐら…..
… ▶続きを読むアンダンテ[andante](伊)
2014年3月19日(水)
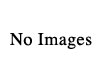
平凡な・・・並みの・・・やや劣った・・・ 人柄が飾らない・・素直な・・・やわらかい 今とか現行のとかの意味もあるそうです。 アンダンテは動詞 andare から生まれました。この動詞が英語のGoと同じ意味です。 前に進む…..
… ▶続きを読むアルペッジオ奏法[arpeggio](伊)
2014年3月19日(水)
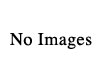
arpeggiare(伊):ハープを弾く、アルペッジオで弾く arpeggio:アルペッジオ 和音を分散してバラバラに弾く事、ギターでは、親指や人差し指で弾きおろしたり 弾きあげたりするストローク奏法に対して、四本の指を…..
… ▶続きを読むアーティキュレーション[articulation]
2014年3月19日(水)
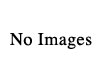
各音の切り方、ないし次の音との続け方を言う。 要素としてレガート(なめらかに続ける)、スタッカート(短く切る)、ポルタート(長めに切る)などがある。 どの方法を選ぶかによって、奏法も大きく変わる事になる。 演奏を生かすも…..
… ▶続きを読む無調/十二音主義[atonality/twelve-tone music,dodecaphony](英) [Zwolftonmusik,Dodekaphonie](独)
2014年3月19日(水)
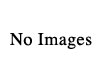
調性感覚を持たないものを一般的に「無調」と呼び、その無調に秩序をもたらすべくシェーンベルク によって創始された「オクターブの12の音の音程関係のみに依存する作曲技法」でかかれた音楽を 俗に十二音主義音楽と呼ぶ。 調性とい…..
… ▶続きを読むアウフタクト[Auftakt](独)up-beat(英)
2014年3月19日(水)
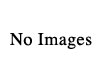
日本語では「上拍」といい、指揮棒が下に向かって打ち下ろされる強拍(下拍)に対して、上に向けて振り上げられる弱拍のこと。 しかし一般的には、旋律やフレーズの始まりにおいて、最初の強拍(あるいは小節線)に達する前の部分から始…..
… ▶続きを読むバランス[balance]
2014年3月19日(水)
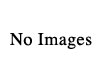
複数の楽器やパートが同時になったときの音量や性格の配分、ソロパートと伴奏の音量配分、ハーモニーを鳴らしたときの各パートの音量配分、各楽章の性格つけ配分などを主にさす。 コンサートにおける楽曲の配分などをさす。 「音のバラ…..
… ▶続きを読むバンダ[banda]
2014年3月19日(水)
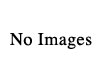
ホールや劇場の空間のなかで、ステージ(オーケストラ・ピット)以外の場所で演奏して特殊な効果をあげるように指示された別の楽団のこと。 最も多いのは、オペラの舞台で衣裳も着けてお話の中の楽団としてステージ上で演奏するものです…..
… ▶続きを読むバロック[baroque](仏)(英)[barocco](伊)
2014年3月19日(水)
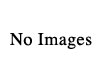
バロック[baroque](仏)(英)[barocco](伊) ポルトガル語の「いびつな真珠」という意味の言葉からきている。 音楽史の17世紀初頭から18世紀半ばまでの時代区分としてこの名前を使われるようになったのは、 …..
… ▶続きを読む